−『ico』分析による実証−
作品を造り込むタイプの作家にとって、「すごく共感できました!」という感想は、褒め言葉ではないく、むしろ貶し言葉の部類に入る。このタイプの作家たちが目的としているのは読者を感動させたり、悲しませたりといった単純な感情操作ではなく、感情操作ができるのは当たり前のこととして、その上でどのような物語を構築できるかということだからである。彼らにとって読者の感情を操ることなど朝飯前であり、単純に楽しい物語や哀しい物語を書くのは健全な男子にヌードグラビアを見るがごとき行為なのである。ただの生理現象なのだ。ただ読者の共感だけを求めるテクストなどエロ本も同然、誰にだって書ける。彼らはそう思っている。
では、彼らがそう考える理由、根拠は存在するのだろうか?「これを書けば読者を悲しませることができる」「これを書けば読者を感動させられる」というようなコード化された物語の定石など存在するのだろうか?それともただ彼らの経験から捻出された経験則があるだけなのか?もし、おもしろさの論理的根拠というようなものがあるとすれば…
「ありえない!!」確かにその通りだ。なぜなら、そのようなコードは時代や社会状況(コンテクスト)によって大きく左右されてしまうからである。そして人間に個体差がある以上、同一のコンテクストなど望むべくもないのは当たり前の話である。
しかし一つのテクストの中にこのコード化された物語の定石(ロシア・フォルマリストの言葉を借りれば物語素)が多数埋め込まれていれば、そのうちのいくつかは機能することが期待できるだろう。100%機能する必要など無いのだ。また機能しやすい物語素を厳密に選べば、さらにその可能性が高くなる。例えば小説、100ページのテクストの中にこの物語素が20個ほど埋め込まれているとしたら、半分の10個が機能すればそのテクストは無邪気な読者(ただ共感するだけの読者)にとっては面白い小説となるであろう。10ページに一回は面白い部分にぶつかり、場合によってはその面白さが100ページ続くことになるかもしれないからである。10ページだとしても読書スピードが1分1ページとして10分に一度は新たな楽しさが顕れる計算になる。読むのが速ければよりスピーディーに楽しめる。これほど効率のいいエンターテイメントが他にあるだろうか?(笑)
たしかに、構造主義者が使う物語素という概念は物語構造を語る上では既に機能しなくなっている。ロシアフォルマリストが物語素のサンプルとして提出した数百個の欧州の神話に類似しない、あるいは含まれない要素を持った物語もあるからであり。過去(フォルマリストの言う物語素)の破壊を目論むモダンや、アイロニカルでメタ的な楽しみを提供する過去の再利用ポストモダンなどは物語素で語ることは出来ないし、あらゆる物語はモダンとポストモダンの要素を少しは持っているからである。物語素で語れるのは、神話など古来から使われる物語の定石が、彼らのコードに乗っ取って進行する場合でしか使用できない。しかし、私が物語素に求める機能はそれだけで十分だ。物語素だけで物語を再構成できる必要などどこにもない。そんな絶対性など求めていない。物語素はコードに乗っ取った物語進行の場合にのみ機能する、それだけも十分有効な理論である。モダン(過去の破壊)やポストモダン(過去の再利用)を分析するのにはまた別の手法を用いればいいだけの話なのだ。
つまり物語素は第一レベルのモデル読者(共感するだけの読者)を想定した場合に有効なのであり、第二レベルのモデル読者(解釈する読者)や第三レベルの読者(ゲームする読者)を想定した場合はあまり機能しないのであるし、また機能させようとする必要など無いのである、そこにはまた別に手法があるのだから。(ちなみに第一レベル、第二レベルなどと分けてはいるが、私は第一レベルに比べて第二レベルの方が高度な読み方だと主張しているのではない、便宜的にただカテゴリー分けをしただけである。)
物語素は限界をとうに見透かされた概念ではあるが、「おもしろさの論理的根拠」を物語レベルで提出しようとした最初の試みであっただろう。本論ではこの「おもしろさの論理的根拠」を提出しようとした試みの歴史を簡単におさらいすると共に、仮説として人が体験する通過儀礼もおもしろさの論理的根拠として使えないだろうかという試みに入る。
1.「先行研究の整理と理論構築」 ※ここから『ico』論に密接に関係
1.1.「おもしろさの論理的根拠、探求の歴史」
この手の学問として最初に確立されたものとして修辞学を忘れてはならない。今でこそ廃れた学問ではあるがアリストテレスからヴィーコに至るまで連綿と築き上げてきた歴史は決して無視できるのものではないからである。最近は修辞学を広義で捉えたがる傾向があるようだがここでは修辞学を狭義で捉え、暗喩(メタファー)やメトニミー(換喩)といった文彩の技法に焦点を当てたい。ロシアフォルマリストが物語のなかに面白さの素を抽出しその機能と属性を研究したのに対し、修辞学では物語以前の問題、文章のレベルでのおもしろさの論理的根拠を提出したのである。
修辞学に続くのが先に挙げたロシアフォルマリストの研究であろう。彼らのテーゼに関してはもはや触れることもない。「物語素だけで物語を再構成できる」という考え方と、物語素のサンプルとして古来から伝わる数百個の欧州の神話を用いた。ということが整理できれば十分である。ウラジミール・プロップの『昔話の形態学』では「魔法物語」に分類される昔話を土台にした物語の文法が記号化され、物語素の機能と属性が詳しく解説されており、その進行の仕方まで綿密に分析されている。この一冊さえ押さえておけばここまでの流れは十分に把握できる。
彼らの論理保証の土台は何百年、何千年と語り継がれた神話という時の洗練を受けたものである。かみ砕いて言えば、何百年も語り継がれて消えないものはつまり、最高のベストセラー作品であり、とすればそれを構成する物語素、物語の文法はまちがいなく面白さの素であるはずだ、ということだ。この考え方の欠点については前に述べたとおりである。
次に何と行っても古来からの伝統的な方法である手法を忘れてはならないだろう、「剽窃(パクリ)」だ。ただの剽窃に理論など無かろう、過去にヒットしたテクストの面白さの核を直感的にくみ取って奪ってしまうのがいわゆる剽窃だ。剽窃の論理保証は既にヒットしたテクストを素にしているというところにある。一度みんなに受けたのだから、また次も受けるだろう、という考え方だ。しかしこの場合、剽窃だとバレた時点で(道徳的問題で?)効力が著しく薄れるという欠点がある。
その剽窃を理論化し、発展させたのがポストモダンである。こういう言い方は失礼であろうか?しかしひと言で言うのならこう言う以外あるまい。
過去の利用といえば聞こえはいいが、既に在るテクストの力に乗っかっているという意味では剽窃と変わるところがない。ポストモダンの論理保証は剽窃と同じように、既にヒットしたものを土台とする。また、ただの剽窃の場合は欠点であった道徳的問題は、「引用である」という道徳的理由付けがあるため、解消されている。そしてそれプラス、パロディー、キッチュなどポストモダンの最も特徴的な面白さが付与されている。読者との共犯関係を作り出せる、という点で物語素で分析できる範囲を超える面白さを演出できるということだ。
こうしてみてくると、面白さの論理保証とそれ+αという点でポストモダンは欠点がない。現時点で最強の手段だと言えるだろう。
ポストモダンにおいては、引用(剽窃)をオリジナルと勘違いして、物語に共感することを楽しむ、第一レベルの楽しみ方がまず基盤として用意され、引用を引用と見抜ける人には「その引用が巧妙であるかどうか?その意味はなにか?」を解釈するという第二レベルの楽しみ方が用意されている。これは、あらゆるテクストにメタ的な要素があり、あらゆるテクスト、記号に他のテクストや記号とのリンクがある以上、どのテクストにも当てはまることだろう。
「物語素」ではその第一レベルしか説明できないが、しかし第一レベルの面白さもやはり第二レベルの面白さを語ることと切り離しては考えられないだろう。なぜなら第二レベルの面白さは常に第一レベルの面白さに影響を与え続けるものだし、逆もまた然りだからである。第二レベルの面白さを第一レベルの面白さとひっくるめて総括的に論じることは現段階での私の力量不足と時間的リソースの問題でできない。よってここではひとまず「通過儀礼」による第一レベル、第二レベルの面白さの論理保証を論じるに留まろう。もちろん、いつか総論的な論文が書ければとは私も思っているが…
1.2.「通過儀礼」
「修辞学」「物語素+物語の文法」「剽窃」「ポストモダン(引用・キッチュ・パロディ)」の四つが、現段階においておもしろさの論理的根拠として整理できる。もちろんただ整理しただけでは面白くも何ともない論文であるから、この四つに加えて、もう一つの面白さの根拠について仮説を展開していきたい。
それは「体験」である。人間は誰しも体験に基づいた想い出を持っているものであり、他人から見ればちっぽけでありきたりな想い出にもその人独自の思い入れがある。ということは人々がしてきたその体験を物語の中で思い起こさせることができたら物語によって人々の「体験」の想い出を刺激し、呼び起こすことが出来れば、読者はテクストのストーリーに自分の体験をプラスしてファーブラを作り出すに違いない。テクストというのは怠惰なシステムであり、全てのことを記すわけにはいかないから常に読者に共同作業を求める、読者に足りない部分を想像せよ、物語れ!と要求する。仮に読者がその足りない部分を自分が大事にしている体験の想い出によって埋めるとすれば、その物語はその読者によって最高の一冊になるに違いない。
しかしどうやってその「体験」の想い出を呼び覚ますのか?「体験」など人それぞれで、種類も星の数ほどある。「体験」の想い出を呼び覚ますスイッチを設定したとしてもそのスイッチが有効に機能する人は一万人に一人かも知れない。これでは意味がないし、理論などではない。
ここで私がその「体験」の想い出を呼び覚ますスイッチとして提案したいのが「通過儀礼」である。「通過儀礼」と言う言葉が耳慣れない方のために簡単な説明を加えると、これは「成長していく過程で誰もが体験すること」であり、その体験なくしては子供から大人になれないような体験のことである。勿論、文化によって異なる場合もあるし、同じである場合もある。「元服」は過去の日本の文化では通過儀礼であるが、現代日本では通過儀礼ではない。しかし「誕生」や「死」は文化を問わず、誰もが必ず通る通過儀礼であるし、「結婚」、「出産」、「親の葬式」などもかなり高い確率で、どの文化でも起こりうることである。
話を戻そう。この「通過儀礼」は人に忘れえぬ強烈なインパクトを与えるものである。「死」というのは常に哲学のモチーフになってきたし、「結婚」も良し悪しはともかく、深い想い出となることは間違いない。そしてその想い出は極めて個人的なものであり、他人から見ればちっぽけでも、本人にとっては極めて重要なものである。
このように強烈なインパクトを与える通過儀礼は、通過してきた人に必ず大きな「体験」の想い出を与えていると予想できる。人はその通過儀礼のことを思い出すたびに、自分の中の想い出と再会することだろう。そしてその想い出は、良い想い出であっても、嫌な思い出であっても人の心を強烈に揺さぶるものなのではないだろうか?物語中で通過儀礼を描いてやれば、それがスイッチとなり、それにまつわる想い出が読者の心に蘇ってくるのではないか?
例えば「初恋」という通過儀礼は太古の昔から現在に至るまであらゆる物語に使われているが、我々読者は物語中で描かれる「初恋」という通過儀礼に触れることで、自分が体験した「初恋」と照らし合わせ、想い出が蘇ってくるのを楽しんだり、「ああ、あのときこうしていれば…」と後悔したりしているのではないか?通過儀礼は、人が最も大事にしている想い出へのスイッチなのだ。
わかりやすさを増すために図を記しておく。
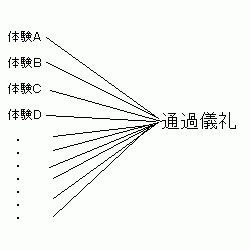
1.3.「通過儀礼は修辞学によって汎用性を増す」
内 しかし、「体験」のスイッチを入れるために、通過儀礼を「初恋」なら「初恋」というそのままの枠組みでテクストに組み込まなければならないのだろうか?だとすると通過儀礼の用法はかなり限定されてしまう。しかしここには、暗喩(メタファー)や換喩(メトニミー)といった修辞学的技法が使えるのではないだろうか?
先ほども使用した「初恋」という通過儀礼を例に挙げて論証すれば、各個人が体験した想い出を引き出すスイッチとして「初恋」を用い、さらにその初恋をメタファーやメトニミーによって言い換えることが出来るのではないだろうか?例えば「同じクラス、隣の席の女の子をイヂメた(からかった)」という物語を書けば、明確に「初恋」という肯定を辿らなくともメトニミーとして「初恋」というイメージに結びつき、それが個々の想い出を喚起する。図式的には、以下のようになるだろう。
「隣の女の子をイヂメる」→通過儀礼「初恋」→個々の「体験」の想い出
↑
メトニミー
この場合、「隣の女の子」は「幼なじみ」でもいいし「近所の綺麗なおねえさん」でも同様の機能を果たすだろう。
また仮にこの例でメタファーを使うとしたら、どうだろう?「初恋」を暗示するモノ、いろいろあるだろうが、カルピスのCMがまだ「初恋の味」をキャッチフレーズにしていた世代にならカルピスは初恋のメタファーとして作用するだろう。図式的には以下のようになる。
「カルピス」→「初恋」→個々の「体験」の想い出
↑
メタファー
もっと汎用的なメタファーを例示するとすれば、「いちご味」などどうだろう?「甘酸っぱさ」をコノテーションとして持つ「いちご」は初恋のメタファーとして、いかにも'80年代アイドル歌手の歌詞などに使われていそうな雰囲気がある。
「いちご味」→「初恋」→個々の「体験」の想い出
↑
メタファー
このように通過儀礼「初恋」をさまざまなメタファーやメトニミーによって暗示することが出来れば、「初恋」に付随する個々の体験を呼び覚ますスイッチの幅はより広がり、多様性を増す。つまり「初恋」のメタファーやメトニミーであればどんなものでも個々の想い出を喚起するスイッチたりえるのだ。解りやすく図で示すと次のようになる
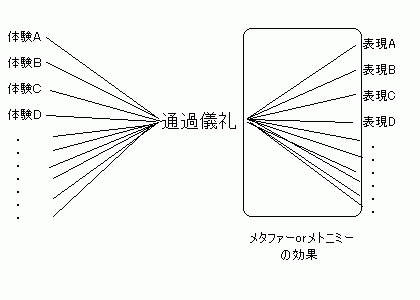
これは通過儀礼というスイッチを使う、おもしろさの論理保証を消すことなく、修辞学の残した遺産を使って、その表現の多用さを獲得できる利点がある。つまり物語レベルで面白さの論理保証を持つ筋立てをしつつも、ありきたり、紋切り型と読者に思わせないような文彩の巧妙さを文章レベルで手に入れることが出来るのである。
1.4.「仮説の暫定的結論」見出し
「体験」の想い出は人の数だけ存在するが、スイッチである通過儀礼に関して言えばそれほど多くはないし、少なくとも一つの文化圏において「誰もが皆」通過する体験を通過儀礼というのだから、かなり限定して想定することが可能である。ということはその通過儀礼を物語の中で再現すれば、読者の個人的な想い出を引き出すことが出来るのではないだろうか?
厳密なマーケティングを行えば、読者対象がどのような通過儀礼を体験しているかはかなり詳しく想定できるだろうし、「初恋」などある種普遍的な通過儀礼に関して言えば大して調べなくとも想定は楽である。
「初恋」という通過儀礼を使うとすると、その物語レベルでのパターンは限られ、新鮮味が斬新さが失われる危険があるが、メタファーやメトニミーといった修辞学的技法で文彩を加えることが可能であり、通過儀礼のスイッチとしての幅も大幅に広がるものである。
ということは通過儀礼はおもしろさの論理的根拠の一つであると言えるのではないだろうか?この仮説を実証すべく、『ico』というゲームを当てはめて分析してみたい。
ゲームを語ろうへ戻る
沢月亭 へ戻る